読書ノート「思考の整理学」
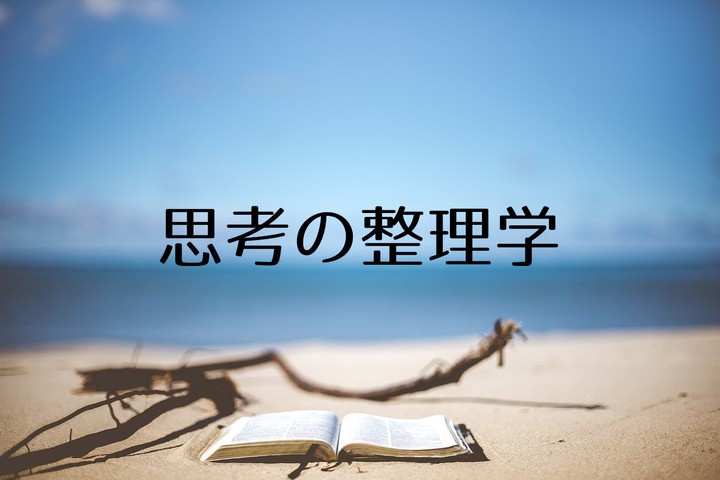
本を読む時間ができたので、読書メモをしようかと。
書籍情報
title: 思考の整理学
author: 外山滋比古
publisher: 筑摩書房
グライダー
- 学校では先生と教科書に引っ張られて勉強する、グライダーのようなものだ。飛行機とグライダーは似ているが、グライダーは自力で飛ぶことはできない。
- 学校はグライダー訓練所、優等生はグライダーとして優秀。
- こどもは労せず詩人であり小発明家。学校で教育されて散文的になり人真似が上手くなる。
- 人間は花を見て枝葉を見ない。
- 新しい文化の創造には飛行機能力が必要。
不幸な逆説
- 昔の塾や道場は教えるのを拒む。学習意欲を高めるため。
- すぐに全てを教え込まない。
- 秘術は隠す、愛弟子は真似ようとする。結果としてグライダー卒業、飛行機人間に。
- 今の学校は教えすぎ、親切でありすぎる。
朝飯前
- 朝の頭の方が夜より優秀っぽい。
- 朝飯の前に簡単でもなんでもないことがさっさとできてしまう「朝飯前」
- 朝の頭は能率が良く楽天的。
- ブランチ(breakfast+lunch)で朝食を遅らせると昼まで朝飯前の時間。
- いかにして朝飯前の時間を長くするか。
発酵
- 素材を発酵させる、寝させることでテーマができる。
- 見つめる鍋は煮えない、しばらく忘れること。
- 異本論について、Aを読んで理解するのは異本A’で決してAそのものではない(六法全書は異本を少ししか許さない)
- 熟したテーマは向こうからやってくる
寝させる
- 英語成語: “over sleep” 一晩寝て考える
- 「朝から晩まで考え続けた」はこだわりができ、大局を見失う。
- 幸運は寝て待つ
カクテル
- 「ひとりでは多すぎる。ひとりでは、全てを奪ってしまう。」(アメリカの女流作家ウィラ・キャザー)
- 「ひとり」は恋人のこと
- 1つだけでは、多すぎる。
エディターシップ
- イギリスの詩人批評家、T・S・エリオットは「人生に一度も本を書かなかった」
- 編纂するのであって、書き下ろしがない
- 独立した表現が全体の一部になると性格が変わる。
- 何をどういう配列で並べるか。
- 「詩とは最も良き語を最も良き順序に置いたものである」
触媒
- 新しいことを考えるのに自分の頭から絞り出せる、は愚問。
- 既に存在するものを結びつけることで新しいものが生まれる。
- 焦る、緊張するのはものを考えるのに不要、心をゆったり、自由に。
- 優れたカクテルを作るには小さな自我は抑えて良いものと良いものが結びつくように。
- 発想の母体は触媒としての個性。
アナロジー
- 慣性の法則
- 視覚における残像現象
- 心理的残像
- 外国語などで辞書引くと言葉と言葉が離れ離れになるが、思い切って早く読むとかえってよくわかる、修辞的残像
セレンディピティ
- 潜水艦の機関音を捉える目的の実験がイルカの交信の発見に
- 行きがけの駄賃のようにして生まれる発見(セレンディピティ)
- 語源は「セイロン(現スリランカ)の三王子」という童話、よくものをなくし、探し物をするが狙うものは一向に出てこず、予期しないものを掘り出す。
- セイロンはセレンディップと呼ばれていた。
- 周辺的関心>中心的関心
情報のメタ化
- 人為としての情報は高次の抽象化へ昇華
- 思考の整理は低次の思考をメタ化していく、それをしなければ単なる思いつき
スクラップ
- たまには捨てる。
- 贅肉を落としていかないと動きが取れなくなる。
カードノート
- 出典、何という本の何ページからとか。
- 見出しをつけておくこと、内容を簡潔、的確に示す。
つんどく法
- テーマに関連のある文献を集められるだけ集める。
- 頭の中に記録していく。記録した安心感が忘却を促進。
- はじめの一歩が最も時間を食うのでより標準的なものを読む。
- 読み終えたらなるべく早くまとめの文章。
- 自分の頭をノートに、カードに。
手帳とノート
- 手帳の中でアイデアは小休止、寝かせる。
- メタ・ノートでさらに抽象化。
整理
- 人間の頭は倉庫として考えられてきたが、新しいことを考え出さなければならないのも事実。
- 睡眠が必要。
忘却のさまざま
- 転地効果でリフレッシュ。
- やけ酒とかはNG
- 難しい本をわかろうとして読むとかえって落ち着く。
- 忘れる時は別のことをする。
- 汗を流す、血の巡りをよくする。
時の試練
- 流行の色眼鏡をかけて見てしまう。
- 時間をかけて変わるべきところは変わらせる必要がある、いわば時の試練。
- 優れたものは語り継がれる。
すてる
- 「知識それ自体が力である」ベーコン
- 収穫逓減の法則に似た、知識逓減、はじめは勉強すればするほど能率が上がっていくが、かなり精通すると壁につき当たる。
- 不要なものはどんどんすてる。
- 意識的にすてるのが整理。
とにかく書いてみる
- 気軽に書いてみる。
- 気負わないこと、構想はゆるくても良い。
- 文章は欲を出すと逆効果で、書けないと思ってる時でも、もう書けると自分に言い聞かす。
- 書いているうちに頭に筋道ができる。
- 書き出したら先を急ぐ、全速力の自転車が少しくらいの障害をものともせずに直進するように。
- 推敲する。
テーマと題名
- 大雑把な題名が好まれる。
- 修飾語を多くつけると表現は弱くなる、修飾を多くすると厳密になる場合もあるが、不用意に行うと伝達性を損なう、厭味になることも。
- 三上章(あきら)の『象は鼻が長い』は一見童話に見えるが、実は二重人格を扱った日本文法論。
ホメテヤラネバ
- ピグマリオン効果: 40人をA,Bに分ける(平均点は同じに調整)。Aには採点した答案を返すが、Bにはテストの成績は良かったと告げる。何度か繰り返すとBの方が点数が高くなる。
しゃべる
- 原稿は黙って書くが、読み直しは音読する。声は思いの外、賢明。